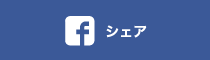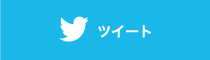Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
―ガラガラガラガラ…
ーコロンッ
『はい、4等の商品券でーす!』
キャンペーン用の法被(はっぴ)を着た店員さんがそう言うと、私たちの前の前に並んでいた女性はガラポンから手を離し、商品券を受け取り去っていく。
「いよいよ次だね、大介(だいすけ)」
「うん」
「…ごめんね、一緒に並んでもらっちゃって。人が多いところ苦手なのに」
「うん、まあ、あとちょっとだから大丈夫」
本当は大丈夫じゃないのに、大介は帽子を深く被ったままそう答える。
そんな彼の様子を見て、私は彼をショッピングモールに連れ出してしまったことを少し後悔していた。
きっかけは、私と大介の休日が重なったことだった。
警備員である彼のシフトは不規則だ。私は土日休みだけど、彼は仕事になることが多く、普段はなかなか休みが重ならない。
でも、今回久しぶりに休みが合ったので、それならたまには一緒に映画でも観に行こうと、近所にあるショッピングモールに誘ったのだった。
せっかく日曜日にショッピングモールに行くんだから、ついでに特売の「お一人様一点」の卵を買うのに付き合ってほしい…私は彼にそうお願いし、彼は承諾した。
そうして、卵やら何やら買い物をしたら、今度は抽選券を2枚もらってしまって…せっかくだから二人で1枚ずつ引こう、ということになり、今に至る。
優しい彼が何も言わずに付き合ってくれるものだから、つい勝手に進めてしまったけど…元々こういうところが苦手な彼を無理やり連れ回してしまって、なんだか申し訳なくなってきた。
「陽子(ようこ)。順番きたよ」
「え? あ、うん」
と、そんな罪悪感を感じている間に、いつの間にか順番が回ってきていた。
大介に声をかけられ気づいた私は、こうなったら1等の温泉旅行ぐらい当たってほしいと思いながら、ゆっくりとガラポンを回す。
―ガラガラガラガラ…
ーコロンッ
『残念、ポケットティッシュですねー』
「……」
気合を入れて回したものの、私も、私の後に回した大介も残念賞のポケットティッシュだった。
せっかく並んでもらったのに…。
ますますばつが悪くなって、私は彼に頭を下げる。
「本当にごめん」
「それより、陽子。何かクーポンついてるみたいだよ、これ」
「え?」
大介に言われ、ポケットティッシュの中に挟まった紙を見てみると、それはなんと、これから行く予定だった映画館の300円引きクーポンだった。
「おお、ラッキー!」
「良かったね、並んで」
小さなラッキーに私が喜んでいると、隣の彼も優しく微笑む。
ああ、並んだ甲斐があってよかった…。
私はほっと胸をなでおろし、彼と共に、映画館のフロアに続くエスカレーターに乗った。
映画を観た帰り道、もらったポケットティッシュが早速役に立った。
「良かったね、ティッシュもらっといて」
「…うん」
時刻はもうすぐ13時。
本当はお昼を食べてから帰ろうと思っていたけど、隣の彼がご飯を食べられる状態じゃなさそうだったのでやめた。
私は彼のかみすぎて赤くなった鼻先に、もう何枚目かわからなくなったティッシュを差し出しながら言う。
「それにしても、そんなに泣く? 割とよくある恋愛映画だったような気がするんだけど…そりゃあ、最後に病気で亡くなっちゃうのは、悲しいけどさ」
「いや、よくある話かもしれないけどさ…なんか、もし陽子が突然あの病気になったらって思うと、泣けてきて」
大介は涙や鼻水をティッシュでふきながら、言葉を続ける。
「昔は全然なんとも思わなかったのに、陽子と結婚してから、こういう映画にすごく感情移入するようになっちゃって。
なんでだろう。家族になったからかな」
てっきり映画の中の話で泣いているのだと思ってた私は、彼の優しい言葉にびっくりした。
びっくりして、少しもらい泣きしそうになった。
ああ、私は幸せ者だ。
さっきのガラポンの時といい、今といい…彼はいつだって、自分のことより私のことを第一に想ってくれる。
こんなに優しい人と結婚できて、本当に良かった。
「わたしは病気になんかならないから、大丈夫」
だから私は、泣かないように元気に笑って、彼の言葉に応える。
優しすぎる彼にも、できる限り笑顔でいてほしいから。
「幸運のお守りもついてるし」
私はそう言って、一緒に選んで買った結婚指輪を彼に見せる。
シンプルな中に、お守りのように大小のダイヤが埋め込まれているのが気に入って選んだ、私の一生の宝物だ。
「…ご利益、あるかな」
まだ悲しい気持ちを引きずっているのか、不安そうな顔でそう尋ねる大介に、私は笑う。
「あるよ。だってわたし、大介と結婚してから不幸になったことないもん。今日みたいな、ちょっとしたラッキーならいっぱいあるけどね」
本当はもっとずっとたくさんの幸せをもらっているけど、まずは、今日の小さな幸せの話をする。
私の言葉に納得したのか、大介は安心したように「そっか」と言って、頬を緩めて笑ってくれた。
あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。