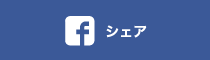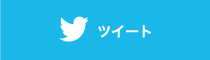Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
交際中の彼女から、日曜日の夜遅くに電話が来た。
「こんな時間にごめん。すぐに私の家まで来てほしい」
彼女はそれだけ言うと、理由も告げずに電話を切った。
突然夜中に電話をかけてくることなんてなかったから驚いた。
俺の彼女は、いつも真っ直ぐで、強くて、俺を引っ張っていってくれる人で…どう考えても、「寂しいから、会いたい」なんて言うタイプじゃない。
「寂しいから」ではないとしたら、何か彼女の身に悪いことが起こったんじゃ…。
「…そういえば、珍しく、真剣なトーンだったような」
想像して急に怖くなってしまった俺は、急いで彼女の家に向かった。
しかし、マンションの玄関前に立っていた彼女・聖子を見て、俺は自分の心配が杞憂だったことを悟った。
彼女は全身に装備を纏っていた。首にはデジタル一眼レフ、肩には三脚、背中には機材が詰まっているであろうリュック。服も寒さに耐えられるよう、少し厚着をしてきている。
「…どこに行くつもりなの?」
「近所の公園。夜遅いから遠くまではいかないよ」
「そう…」
彼女の返事を確認した瞬間、はぁ、と大きなため息が出た。
無事で良かったけど…。何事かと思ったら、写真を撮りに行くのか。
「オリオン座流星群、撮れるかなあと思って」
気を取り直して三脚を代わりに持ってあげると、聖子はそう言葉を足した。
「オリオン座流星群? この時期だっけ?」
「今日が極大なんだって。私も後輩から連絡来て知ったの」
「ふーん」
「興味ない?」
「んー、流星群は専門外だったからなあ」
「私も専門じゃなかったよ。でも、卒業してから全然星を撮ってないから、なんか久しぶりに撮りたいなって思って」
そんな話をしながら近所の公園まで歩くと、彼女は中央の開けた場所で手早く機材を組み立てはじめた。
大学時代、俺と聖子は天文サークルに所属していた。
天文サークルの活動は大学によってピンキリだ。だから中には長期休みにしか活動しないなんてとこもあるけど、少なくとも俺達のところは、割と本格的に活動していた。
サークルの中でも活動内容がいくつか分かれていて、聖子は天体写真の撮影、俺は惑星の研究をメインに活動していた。
だから二人とも、流星群については詳しくない。
「あ、今光った!」
「え、どこ?」
「ほら、あそこ」
俺はサークル時代を思い出しながら、彼女が指をさす方向を見て、光る星々に目を凝らして、それから…手を伸ばせば触れられそうなほど近くにある、彼女の美しい横顔を見る。
不思議な光景だ、と思う。
サークルにいた頃は、一度だって、こんなに近くに彼女がいたことはなかったのに。
「…なんで、俺だったの」
「ん?」
「なんで俺を選んだの。大学の頃、あんなにモテてたのに」
聖子に突然告白され、付き合って欲しいと言われたのは、サークルを引退した後…卒業3ヶ月前のことだった。
彼女は美人で、サークル内でも、学校内でもアイドルだった。
おまけに理系で頭も良くて…文系の俺とは共通点も釣り合う要素もないのに、何故か俺が恋人に選ばれた。
「んー…なんていうか、普通の男じゃだめなんだよ。
真面目だけど、変わってる男がタイプなの」
「…なるほど」
「自覚あるの?」
「いや、そういうわけじゃ」
文学部を出て地方公務員になった俺のどこが変わった男なんだろう。
一瞬納得しかけたけど、即座に否定する。
「でも、”話が長すぎる惑星オタク”として有名だったじゃん」
「いや、それは研究対象に入れ込んでいるだけで、別に変じゃ…」
「入れ込み方がおかしいから変なキャッチコピーがついたんだよ。恒(わたる)はやっぱり、変わってると思う」
「……」
自覚はないが、変わった男だから選ばれたらしい。
よくわからないけど…それがきっかけで今こうして一緒にいられるなら、何でもいいか、と思った。
光ったように見えたのは一瞬で、その後は全然流星群が見える気配はない。
「流れ星を見たら、恒は何をお願いする?」
退屈に感じはじめたのか、聖子は空ではなく俺の方を見て、そんな質問をしてきた。
「いや、何も願わないけど。願いが叶うなんて迷信だし」
「勿体ないなあ。信じた方が面白いことは信じたらいいのに」
「…じゃあ、聖子は何を願うの?
6億円降ってきて欲しいとか、結婚したいとか?」
「その二択なら、結婚かなあ」
「え」
冗談のつもりで言ったのに、聖子は真剣な表情で答えた。
「お金を稼ぐより、結婚の方が難易度が高いから」
「…そりゃ、そうだろうけど」
返答に困っていると、聖子は急に芝生の上に仰向けに寝転んだ。
そして、視界の先にある空に向かい、ぽつりと呟く。
「あーあ、このまま明日も明後日も、恒と一緒にいられたらいいのにな…」
その瞬間、空にキラリと流星が光り、流れていった。
「…今のは、願い事?」
「そんなつもりじゃなかったんだけど、そうかも」
俺の質問に答える聖子の頬が、微かに赤くなった気がした。
そんな彼女を見て、俺はずっとポケットの中にしまい込んでいたあれを今、渡すことに決めた。
明日言おう、いや、来週の彼女の誕生日に言おう…。
付き合って2年が経ってから、俺は毎日プロポーズを決意しては、挫折してきた。
勇気が出なかった。
ただの惑星オタクだった俺を何故彼女が気に入ってくれたのかわからなかったし、他にいくらでも相手がいるであろう彼女を、俺が幸せに出来る自信がなかった。
でも、聖子は俺とずっと一緒にいたい、と願ってくれた。
だから、俺は彼女の願いを叶えようと思う。
「その願い、叶えてもいい?」
「え?」
幸い、ずっと渡せずにいた指輪は、今日もポケットの中に入っている。
互いを知るきっかけになった、星をモチーフにした指輪『stella』。
星のように輝く彼女にぴったりの指輪を、俺はそっと差し出す。
「結婚しよう」
「…え、え?」
すると、いつも冷静な聖子がパニックになり、「なんで指輪持ってるの?」とか「このタイミングで言うなんて」とか、色々な言葉をぶつけてきた。
その珍しい姿に驚きつつ、俺は彼女をなだめるように言う。
「自信がなくて…ずっと持ってたけど渡せなかった。
でも、今なら俺の願いが叶うような気がして」
じっと聖子の顔を見つめると、聖子は暫く黙った後、小さな声で「ありがとう」と言った。
差し出された手に俺が指輪を通したとき、頭上の星が図ったように再び輝き、空の彼方へ流れていった。
あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。