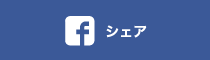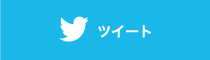Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
―ピピピピ、ピピピピ…
「ん…」
アラームが鳴っている。
ぼんやりした頭で僕はそう思ったものの、布団の外にある携帯電話まで手が伸びない。
面倒なのでやり過ごそうとしたものの、あまりにうるさいので、僕は仕方なくアラームを止め、携帯電話に表示されている時刻を見て…。
「く、9時56分!?」
飛び上がった。
今日、僕は彼女とデートの約束をしていて、待ち合わせ場所には10時に集合で…。
「…あと、4分」
どう頑張っても遅刻だった。
待ち合わせ場所に向かい、僕は走る。
信号をひとつ越え、ふたつ越え、もうひとつ…!
…越えようとしたけれど、最後の信号は赤になってしまった。
「はぁ、はぁ」
普段運動なんかしないから、ひどく息が切れる。
仕方ない。もう30歳も過ぎたし、そもそもこんなに長い距離を徒歩で移動することなんてないし…。
こんなことはあり得なかった。
嫌いだった女性という生き物のために、自分が一生懸命になることなんて。
…あの日までは。
両親に頼まれて参加した婚活パーティ。
これまでの偏った女性づきあいに、出会いを求める場への偏見が手伝って、誰も彼もイケメンか金持ちにしか興味がないように見えていた。
しかし、そこで出逢った彼女は、外見や年収ではなく…僕の趣味に興味を持った。
『素敵な趣味ですね』
『そうですか? 囲碁なんて、地味な趣味でしょう』
『そんなことないですよ。あまり詳しくはないですけど…場面や相手ごとに色々打てる手があって、常に最良の一手を探す必要があるんですよね。難しいだろうけど、面白そうだなって思います』
律(りつ)と言います、と名乗った彼女は、地味な趣味だとずっと笑われてきた僕の趣味を、当たり前のように受け入れてくれた。
そして、彼女は僕が話し終えた後、僕にある不思議な質問をした。
『芳成(ほうせい)さんは、炭酸飲料はどうして泡が出るのか、知ってますか?』
『え?』
『あれは、液体の中に溶け込んでいる二酸化炭素が気体になることで発生する泡なんです。ビールの泡なんかもそうなんですけど』
何故突然、炭酸の泡の話なんかはじめたんだろうか。
どう返したらいいかわからず困っていると、彼女はふふ、と微笑んで言った。
『炭酸飲料の開発研究。それが私の趣味であり、仕事なんです。
地味だけど、色々な組み合わせを考えるの、意外と面白いんですよ』
僕が目を丸くしている間に、彼女と1対1で話せる時間が終わり、彼女は席を移動した。
しかし、その後誰と話しても、もう彼女のこと以外考えられなくなっていた。
「あの日…いや、あの瞬間から、ずっと」
僕は彼女に恋をしている。
その証拠に、走り出す足が止まらない。
もう一度、話がしたい。
もう一度、笑ってほしい。
もう一度…いや、もっとたくさん、あなたと一緒にいたい。
そんな想いが止まらなくなって、パーティの後すぐに、僕は彼女をお茶に誘った。
3回のデートの後、想いを彼女に告げた。
彼女は頷いてくれて…それから、今。
一年が経っても気持ちは変わらないどころか、加速している。
止まらない、このはずむ想いを伝えるために、僕は右手に小箱を握りしめ、彼女との待ち合わせ場所まで走った。
「律さん!」
30分遅れで辿り着いた待ち合わせ場所で、僕は彼女の名前を呼んだ。
「芳成さん」
遅れた僕を嫌な顔せず待っていてくれた彼女に、僕は迷わず想いを伝える。
「ごめんなさい…!
プロポーズの練習してたら眠れなくなっちゃって、遅刻してしまいました!」
小箱の蓋を開け、僕は彼女に指輪を差し出す。
きらめき、弾む、僕の想いのようで…彼女の研究テーマでもある『Sparkling』の指輪を。
「僕と、結婚してください!」
僕が精一杯の気持ちを込めてそう言うと、彼女は少しの間目を丸くして…それから、出会った時と同じように、ふふ、と微笑んだ。
「…こういうのは、本当はもう少し、雰囲気のある場所が良かったんですけど。
でも、眠れないほど緊張して、息を切らして走ってきて…それでここまで頑張ってくれたんだと思うと、雰囲気なんかどうでも良くなっちゃいました」
「…律さん」
「よろしくお願いします。これからも、ずっと」
そう言って微笑む彼女があまりに愛しくて、僕は彼女を抱きしめる。
ドキドキと高鳴る心臓の音を感じながら、僕はこんな気持ちがこれからも、いつまでも続いてほしいと思った。
あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。