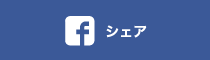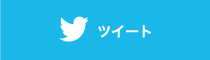Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
ホテルにフロント係として採用されて7年。
初めこそ戸惑ったものの、仕事には慣れた。
お客様の応対は基本は引き受けた自分が最後まで丁寧に、しかし時には他の人に引き継いだり、お客様自身で解決できる方法を案内したりする。できるだけ平等に、多くのお客様の要望に応えられるように、かつ本来の業務に滞りないように立ち回る。
いつの間にか仕事ぶりを評価され、支配人候補として多くの仕事を任されるようになった。上がった立場や給料に見合う時計や靴などを買うようになった。
異性にもモテるようになり、何人かと交際した。異性との交際はそこそこ楽しいけれど、最終的に魅力を感じられなくなり、別れることが多かった。
順調すぎて、刺激が足りない毎日…いつものようにフロントで受付をしていると、よく見かける”彼女”がやってきた。
名前は白石裕美(しらいし ゆみ)。国内ツアーの添乗員をしている彼女は、いつもツアー客の老若男女に振り回されてあたふたしていた。
「添乗員さん、疲れたー。もう部屋行っていい?」
「ねえ、お風呂は何時から入れるのかしら」
「あ、バスに忘れ物したかも。ガイドさん、ちょっと取りに行きたいんだけど」
彼女はこれらの要求に「今確認しますね」と一つ一つ応じ、確認しては案内していた。
慣れていないのか、時にはお客様を待たせたり慌ててどこかに走っていくときもあって…。
いつもぺこぺこ頭を下げていて、全然スマートじゃない。
見ているこっちが心配になるような人だった。
そんな彼女の印象が変わったのは、ある夏のことだった。
その日、彼女が案内するツアー客のチェックインが予定の時刻より少し遅れた。
どうやら、お客様の中に暑さで体調を崩した人がいたらしい。
そのお客様を病院に運んだ後、急いでホテルまで来たのだそうだ。
その後、夕食までには戻ると言って彼女は病院に向かったが、時間になっても戻ってこなかった。
結局連絡があったのは、夕食の提供時間が終わる数分前だった。
「すみません、今ようやく戻れそうなんですが、夕食をご用意いただくことはできますか?」
「申し訳ありません、今からだと難しいですね…」
うちのレストランは、提供時間終了の30分前までに料理を注文してもらう形になっている。
今からこちらに向かうのでは到着自体も間に合わないし、申し訳ないが夕食は諦めてもらうしかない。
しかし、彼女は引き下がらなかった。
「お客様の分だけでいいので、どうにかお願いできませんか?
時間的に難しいことはわかっています。でも、今回結婚10周年の記念で、わざわざ遠くからいらした方なんです。美味しい夕食で、旅の思い出を作ってあげたいんです!」
納得してもらえるかと思っていたので、そう言われて驚いた。
普段見かける頼りない態度とは全く違う、真剣な声だった。
「…わかりました。提供できるか、確認してみます」
彼女の熱意に押された俺は、レストランに確認をすることにした。
予想通り無理だと言われた。こういう場面で俺が求められている仕事は、やっぱり無理だと彼女に説明し、納得してもらうことだった。
それはわかっていた…けれど、この時は何故かどうにかしなければいけないという気持ちが勝り、俺からもレストランに頼み込んだ。
最終的に、何とか一人分だけ用意できることになった。
「ありがとうございます…! 本当に助かりました」
ホテルに戻ってきた彼女はそう言って俺に頭を下げたが、用意できたのはお客様の分だけで、彼女の分の夕食はない。
「いえ、すみません、一名様分しかご用意できず」
俺がそう謝ると、彼女は全く気にしていない様子で「いいんです、役目が果たせれば」と言う。
「お客様に良い旅の思い出を作ってもらうことが、私の仕事ですから」
お客様をレストランまで案内した彼女は、夕食も食べていないのに、その後他のツアー参加者の部屋を巡回し問題がないか聞いて回った。
その姿を見て…自身のことも省みず、人のために、お客様の旅を成功させるために心血を注ぐ彼女を、かっこいいと思った。
本当のかっこよさとは、こういうものだと思った。
俺は今まで、目に見えるステータスばかり大事にしていた。
仕事はこなすものだとばかり考えていた。やるだけはやるけど、ここまでの情熱を持つことはなかった。
彼女を見て自分を恥じた。
彼女のように、一人の人間としてかっこよくなろうと思った。
以降、俺は泥臭くがむしゃらに頑張るようになった。
スマートじゃなくなった俺を見限る人間もいたが、彼らはきっと、俺の外面にしか興味がなかったのだろう。
離れていっても、辛くはなかった。
そんな中、偶然にも、彼女とプライベートで会う機会があった。
俺の姉が、彼女の同級生で友人だったのだ。
近くで彼女に触れ、俺はますます彼女に憧れ、焦がれた。
話せるだけで幸せだった。
でも、欲深い俺は、他の男に取られたくなくて必死にアプローチをした。
それほどまでに、彼女に惚れ込んでしまっていた。
添乗員の仕事を始めて10年。
ツアーの宿泊先でもあるホテルに勤めている彼と結婚することになり、指輪を見に行った。
彼は『White Crown』という指輪を見て、結婚指輪はこれにしたいと言った。
「他に見ないデザインで、二人だけのものっていう感じがするから。
それに、この指輪が一番、俺の君への想いに近いから」
そう言って彼…雅人(まさと)は、『White Crown』につけられたゆびわ言葉を口にする。
「『真心を君に』。
真心を贈りたいと思った。自身を投げうってでも他の人を想う君に、今度は俺が。
…だから、この指輪がいいと思って」
「え…」
その理由に、私は驚く。
溢れるほどたくさんの”真心”を、既に彼からもらっていると思っていたから。
私を好きだと言ってくれた雅人に、ここまでたくさん支えられてきた。休む暇もないほど忙しい毎日の中で、彼がくれるメールが心の支えになった。
もう充分すぎるほど、私はたくさん愛をもらっていると思う。
それに、彼は勘違いしている。
私はかっこよくもないし、ちゃんと欲のある人間で、いつでも自身を投げうつわけじゃない。
自分が大事だから、言うべきだけど言っていないことがたくさんある。本当はこんな高価な指輪、私には勿体ないと思っていることとか。私はあなたに思われるほど立派な人間じゃないこととか。
あなたを手放したくないから、受け入れてしまう。あなたの想いを。真心を。
…なんてことを要約して訴えてみたけど、「それでも裕美は、俺にとってかっこいいお姫様だから」と話を聞いてくれない。
「…それ、褒めてるの?」
「もちろん。ずっと裕美みたいになりたいと思ってる」
「なんか、男らしいって言われてるみたいで、微妙な気分だけど」
ああ、でも、もし私が姫なら、雅人はどんな時も姫に仕える騎士みたいだな、と思う。
いつも私を助けてくれて、想ってくれる。
「まあ、いっか。…ありがとう、雅人」
指輪を試着しながら、私は騎士に感謝した。
不思議なデザインの指輪だけど、不思議と私達に似合っていると思った。
あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。