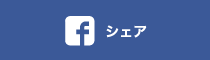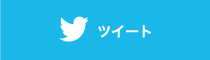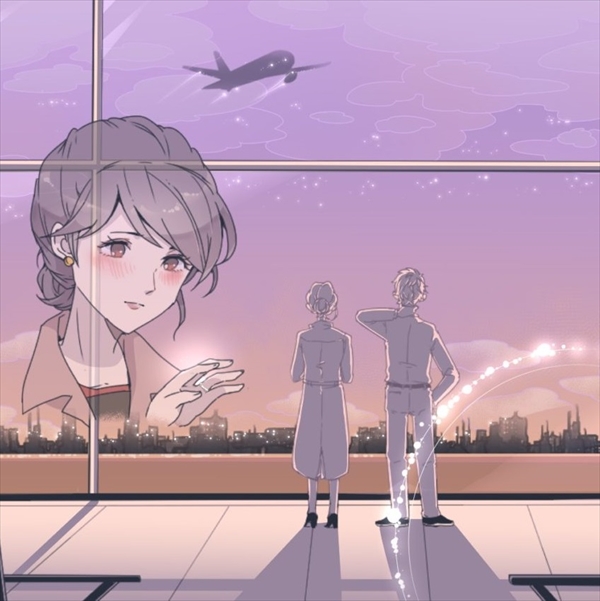Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
「大丈夫、大丈夫。大丈夫だから」
「やだ…」
狭いワンルームの部屋の中。
いくら逃げたって逃げ切れるわけなんかないけど、それでも今は逃げ回る。
「大丈夫だって」
後ろから私を追いかけてくるのは、恋人の亮太。
いつも私を優しく見守り、支えてくれる素敵なパートナーだ。
…でも、そんな彼の優しさを、今だけは受け取りたくない。
そう思っていたけれど、やっぱり逃げ切れず腕を掴まれてしまった。
「こら、逃げるな」
「うるさい。嫌なものは嫌だもん」
「んなこと言ったって、いつかはちゃんと向き合わなきゃいけないんだからさ」
「…わかってるけど」
「なら、とりあえずここに座ろう」
亮太に促され、私は渋々ベッドの上に座る。
「……」
逃げても無駄なら、座って話し合うしかない。
私は隣に座る亮太に向き直り、状況をもう一度説明する。
「裁判官。先程ご説明した通り、数日前に実家に住む母と人生最大の喧嘩をしたばかりなんです。
だから、私、この状況で結婚の挨拶は無理だと思うんです」
しかし、裁判官が下した判決は冷酷なものだった。
「無理じゃない。むしろ謝るべきところなんだから、挨拶も兼ねて謝りに行くべきだよ」
「そんな…」
「ていうか、裁判官ってなに」
「情状酌量の余地はないでしょうか…」
「むしろ汲み取ってる方だと思うんだけど。ねえ亜由美、話逸らさないで」
亮太は私の悪ふざけに付き合う様子もなく、真剣な眼差しで私を見る。
普段は『何事も適度に、楽しく』なんてモットーで生きているくせに、こういうときだけ真剣なの、ずるいと思う。
「…だって」
「だって?」
「どんな顔すればいいか、わかんないもん」
母親と顔を合わせたくなくて飛び出した実家には、もう10年帰っていない。
着る服から食べ物まで、何にでも干渉してくる母が苦手だった。
だから家を飛び出したけど、それで縁が切れるわけもなく…。
しょっちゅう電話がかかってきては、ああだこうだ心配してくるから、つい言ってしまったのだ。
”うるさい、大嫌い”って。
「本当は”大嫌い”なんて思ってないんでしょ?」
「…うん」
「じゃあ、謝りに行こうよ」
「…そうしなきゃ、いけないんだけど」
…いけないんだけど、どんな顔して会えば良いのかわからない。
いい年して情けないけど、不安なのだ。
「大丈夫だって」
固く握りしめていた私の手を、亮太の手が包む。
私より一回り大きくてごつごつした手が、左手薬指の指輪に触れた。
プロポーズされたとき、『fuwari』という名前の指輪なのだと教えてもらった。
『温もり』というゆびわ言葉がついていて、この先ずっと私を温かく包んでいられるように、という意味も込めて選んだのだと…。
それを聞いたとき、感動して思わず少し泣いてしまった。
実家を出てからずっと一人で頑張ってきた私に、そんなことを言ってくれる人が現れるなんて思ってもいなかったから。
いつも黙って見守ってくれて、本当に困っているときだけそっと手を貸し、助けてくれる。
そんな大人な彼を本当に尊敬しているし、いつも迷惑をかけて申し訳ないとも思っている。
「…どう? 少しは落ち着いた?」
「落ち着いてない」
「え、じっとしてたじゃん今」
「…考え事してただけだし」
「えー…。女心って難しいな」
亮太はそう言って肩を竦めたけど、手は握ったままだ。
左手に伝わり続ける体温に、私は思わず「あったかいよね、亮太の手って」と口にする。
「そう?」
「うん…あったかいって、いいよね。安心する」
「お。じゃあ謝りに行く勇気出た?」
「それとこれとは別!」
「えー。一緒だって。
亜由美のことを心配してくれる、温かい場所だって思えばいいでしょ」
「…!」
「ちゃんと帰って、話し合おうよ。亜由美の気持ちも含めてさ」
「…うん」
不安は消えないけれど、亮太の言葉と体温に、少しだけ勇気をもらった。
逃げずに向き合おうと思う。大切な彼と、結婚するためにも。
次の日、私は実家に顔を出すという連絡をするために母に電話をかけた。
「もしもし…お母さん?」
もらった勇気を振り絞り、震える声でそう話しはじめる私を、亮太と亮太がくれた『温もり』がそっと見守り、包み込んでくれていた。

あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。