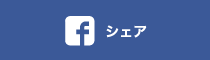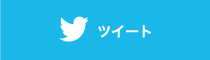Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
「今じゃなきゃ、ダメだと思ったんです」
ある日の仕事中に聞いたその言葉に胸を打たれ、俺はその日、仕事終わりにすぐにジュエリーショップに向かった。
指輪を選ぶ。いろいろあったけど、ダイヤモンドが包みこまれているようなデザインの指輪にした。
オーソドックスなデザインじゃないから受けが悪いかもしれないと言われたが、自分が贈りたいものを優先して選んだ。
今、俺が莉菜を包んで、守ってあげたいと思ったから。
俺と莉菜は、そこそこ有名な某大学の法学部出身だ。
法学部にいた頃は、学部を聞かれ、答える度にこう言われてきた。
「将来弁護士になるの?」って。
法学部で学んだからといって、誰でも弁護士になれるわけじゃない。
むしろ、弁護士になれるのはほんの一握りだ。法学部の中でも一部の人間以外は、法科大学院(ロースクール)の門を叩くことすら許されない。
俺と莉菜は、そのロースクールの門を叩けない側の人間だった。
どうにか行政書士試験だけはクリアできた俺は、卒業後は行政書士として事務所で働くことになった。
一方、莉菜の方は公務員試験の上級に合格した。
今は地方上級公務員として、県庁で働いている。
考え方も成績も近かった俺たちは、学生時代、いつも一緒に勉強していた。期末試験の前は、どちらかの家で夜通し勉強することもあった。
息抜きに出し合ったクイズも、お笑い番組も、夜な夜な食べに行ったラーメンも最高だった。
俺たちは、親友で、戦友で、恋人だった。
しかし、就職と同時に俺たちはそれぞれの仕事に追われ、殆ど会えなくなってしまった。
学生時代は、一緒に暮らしているみたいに、互いの家に入り浸っていたのに。
会う時間も回数もめっきり減り、寂しくなって…それでも、互いに決めた道を進むことをまずは重視しよう、と仕事を頑張った。
仕事の合間に、勉強もした。まだ弁護士になる道も、諦めてはいなかったから。
そうしているうちに、気付けば4年が過ぎていた。
俺たちは共にまだ何の成果も残していなくて、だからたまに会っても、恋人としての将来の話をすることはなかった。
そんなある日だった。仕事で法人設立の代行業務をしていたとき、お客さんである社長がそう言ったのは。
「今じゃなきゃ、ダメだと思ったんです。
たとえ将来、今以上にお金やビジョンを持っていたとしても、今、この熱意があるうちに会社を作らなきゃ、意味がないと思ったんです」
その言葉にハッとした。
今までいろんな理由をつけて、二人の将来のことを…結婚することを先延ばしにしていた。でも、今言わなければ、その将来があるかどうかもわからない。
伝えよう、と思った。まずは今の気持ちを、ちゃんと。
「突然でごめん。
まだ司法試験にも受かってないし、お互い、仕事も忙しいと思うけど…。
でも、今言いたい。結婚しよう」
購入した指輪を受け取ったその日のうちに、俺は莉菜にプロポーズをした。
「そして、一緒に暮らそう。
大変だけど、それでも一緒にいたい」
今の本気の想いを伝えた。
すると彼女は、「…ああ、もしかしたら」と呟いた。
「ずっと私は、賢輔がそう言ってくれるのを待っていたのかもしれない」
そして、そう言って泣き出してしまった。
それから、莉菜は話してくれた。
仕事が辛かったこと。職場で法学部卒として期待されていて、それがずっとプレッシャーになっていたこと。そして、その期待と重圧に押し潰されそうになっていたのを、誰にも相談できなかったこと。
「賢輔だって、自分の将来のために辛いことも頑張ってるんだから、私も弱音吐いてる場合じゃない、頑張らなきゃって思って…。
でも、最初から、素直に相談してれば良かった。そばにいてほしいって言えば良かった。こんなに心が楽になるのなら」
「…莉菜」
「ありがとう、賢輔。
…私で良ければ、これからずっと一緒にいてください」
それから、俺たちは一緒に暮らしはじめた。
仕事はバラバラでも、同じ部屋に帰ってくるというだけで、全然孤独を感じない。
そのことに俺は驚き、そして、あのタイミングで想いを伝えることができて、本当に良かったと思った。
「ただいま」
「おかえり」
残業で遅くなった莉菜が家に帰ってきたので、俺は玄関まで迎えに行く。
少し疲れている表情と左手の薬指を確認し両腕を広げると、彼女は俺の腕の中に思い切り飛び込んできた。
大切な人を包み込むように抱きしめると、大学生の頃と同じようにドキドキして、同じように安心する。
この純粋な澄んだ心を、大人になった今こそ忘れないようにしようと思った。
あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。