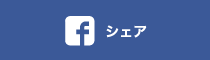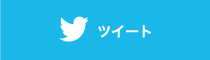Ring Story「ゆびわ言葉®」で繋がる愛の物語をAFFLUX(アフラックス)でチェック!
「あ、これだ」
jeuneという不思議な形の指輪を店で見た花純(かすみ)は、最初にそう口にしたにも関わらず、くるっと俺の方を振り返り、「淳平(じゅんぺい)はどう思う?」と聞いてきた。
普段はそんな風に他人の意見を求めることなんてなかったから、俺はびっくりして、「いや、花純がいいんならいいんじゃない?」と答えた。
「そっか」
花純は俺の目を見て俺の発言が本心であることを確かめると、「じゃあ、これで」と言って店員を呼んだ。
それが、俺たちが婚約指輪を購入したときに起こった出来事だった。
「結婚は特別なことだから、人と同じにはしたくないの」
帰り道、花純がそう言うので、俺は黙って頷く。
「でも、一人だけでするものでもないから、ちゃんと淳平の意見も聞いておきたい」
「商品の企画はいつもバッサリ切り捨てるのに」
「だから、これは特別なの」
花純は職場とは違い柔らかな口調で、でも職場と同じようにきっぱりと思ったことを口にした。
プライベートでは呼び捨てにしているが、花純は職場では俺の上司だ。
俺が出すガーデニング雑貨の新商品の企画を、彼女は大体1分で却下する。
1分というのは、企画書を最初から最後まで読み終えるまでの時間だ。
ちゃんと企画書を読みつつも、ピンと来ない企画はどんなに時間と思いを込めた企画だろうとバッサリと切り捨てる…それが彼女の恐ろしいところであり、尊敬できるところでもあった。
自分のことをちゃんと見てくれる、評価してくれる上司に認められるようになりたい。
部下である俺は、その一心で働いていた。
企画が通ったときも通らなかったときも、それぞれ、何故その判断をしたのか理由があるはず…それを俺は、上司の表情を観察しながら考えた。
そうして、観察を続けているうちに、だんだんと彼女の考えがわかるようになってきて…やがて俺は、上司と部下という立場を超えて、少しずつ、花純自身に惹かれるようになっていった。
年の差はあったけど、俺自身も認めてもらえるように、精一杯努力して、告白をして…交際をはじめてから2年後の昨日、ようやくプロポーズをすることができた。
プロポーズをしたとき、彼女は企画書を読むときよりも長い時間、沈黙した。
それから、「わかった」と、一言だけはっきりと答えてくれた。
「庭を作りたいんだ」
「え?」
「結婚して一緒に暮らすことになったら、庭を作りたいってずっと思ってた」
「…ごめん。一緒には暮らしたいけど、さすがに庭付きの一戸建てを買うにはお金が…」
今は無理だけど花純の望みなら仕方がない、どうにかしてお金を貯めよう…俺がこっそりそう決意しながら脳内で資金調達案を練っていると、花純は俺の思考をぴしゃりと遮り言った。
「大丈夫、そこまでは求めてないから」
「え」
「…そういうのじゃなくてね」
戸惑っている俺の目を花純の目がしっかりと捉え、見つめてくる。
俺も見つめ返し、完全に目が合った後、花純はゆっくりと話しだした。
「昔、母が、家の小さな庭を立派に作ってくれたんだ。友達の家の立派な庭が羨ましくて、うちもこういう庭がいいって、母にお願いしたの。
元々の広さが違ったから、当然、友達の家の庭みたいにはならなかった。
でも、母が一生懸命工夫して飾ってくれたうちの庭が、私は一番好きだった」
彼女が人の目を見つめるときは、自分の中の大切な思いを伝えるときと、相手の本心を聞きたいときの二つしかない。
「だから賃貸の小さなベランダみたいなところでもいいから、将来、家族になる人と一緒にガーデニングができたらなって、ずっと思ってたんだ」
だから俺は、花純がずっと大切に温めてきた気持ちを、正面から受け止める。
「わかった。やろう」
「本当に?」
「もちろん。いいじゃん、ベランダガーデニング。狭い方が細かい装飾にこだわれるし、部屋に近い分世話しやすいし」
それに、家で色々試せるなら、却下されないような商品のアイディアも思いつくだろうし…なんて冗談交じりに俺は言葉を付け足す。
けれど花純はクスリとも笑わず、何故か真顔で驚いたような顔をしていた。
「……」
そのまま彼女が沈黙するので、俺は慌てて「何かまずいこと言った?」と尋ねる。
すると彼女はゆっくりと首を横に振り、柔らかく微笑んで言った。
「淳平はすごいな、と思って。狭い場所でも、その狭さを楽しむ方法をすぐに思いつくから」
ピンと来ないものをバッサリと切り捨てる彼女は、ピンと来るものを真っ直ぐに褒める。
…たまにこうして、褒める相手に眩しいくらいの眼差しを向けながら。
「何でも真剣に受け止めて、そこから新しい発想を生み出す。
淳平の瑞々しい目を見ていると、どんな無茶なことも叶いそうな気がする」

あなたのお近くにある
アフラックスの店舗をぜひお探しください。